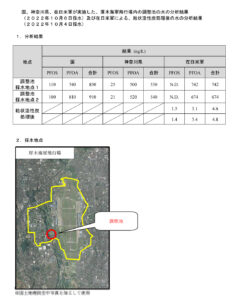インクルーシブな就労
産業労働常任委員会、今年度の最終日には、障害者雇用について取り上げました。
 障害者雇用
障害者雇用
障害者雇用は、雇用促進法において、雇用率というハードルをもったことで勢いをもって推進されてきました。この法定雇用率も2.7%に段階的に引き上げられていきます。
また、新たに「就労選択支援」という就労に向けたアセスメントを行う機関が創設されます(相談支援事業など多くの課題がある中で、どこがこの事業を担うのか、まだ不透明な部分がありますが)。神奈川県では、「障害者雇用促進法」と「障害者総合支援法」という二つの法にまたがり、労働雇用と福祉が連携して行なっていることから、産業労働局と福祉子どもみらい局という二つの局にまたがる事業として進められています。
就労訓練事業
合理的配慮を必要とする働き方は、障害者雇用以外にもあります。
生活困窮者自立支援制度に基づく就労支援がその一つです。こちらは、就労と名前がありながら、福祉の事業としてのみ扱われており、県の「雇用・労働」のページにも載っていません。
生活困窮者自立支援制度においては、生活に何らかの困難を抱える人などと、対象が幅広く設定されています。精神障害を抱える方や、グレーゾーンの方が多くいるということも特徴です。就労支援には、就労訓練事業いわゆる中間的就労等があり、この事業所の認定は県が行なっています。事業所の開拓などについては、昨年度委託事業が終了し、県が直接行うことになるとのこと。事業所に向けた支援も市町村に委ねられ、サポートが薄くなるのではと懸念しています。産業労働局の持つ障害者雇用の知見や、企業のネットワークが間違いなく生かされる分野でありながら、連携がされてこなかったことを、常任委員会では、指摘を続けてきました。
インクルーシブな就労
自治体によっては、こうした就労支援を一体的に行って実績を出しているところもあります。
神奈川県も障害者雇用における手帳の所持といったハードルを下げようといった国への働きかけは行なっていますが、将来的には、障害者といった括りにすらこだわらず、誰でも配慮が必要になれば、その支援を受けられるユニバーサルな働きを推進していける体制が望ましいと考えます。
神奈川県も教育分野では、フルインクルーシブ教育の実現に向けて一歩踏み出そうとしているところですが、教育や福祉だけでなく、教育の先には、就労の場があり、同時に全ての部局がインクルーシブ社会に向けて環境を整えていくべき。と、委員会においても提案しました。
労働部長からは、福祉との連携をすすめ、多様な働き方を推進していくと答弁がありました。
障害があっても、またそれを受容していなくても、働きにくさを抱えた人と共に生き、働く、インクルーシブな社会に向けて、政策提案をつづけます。